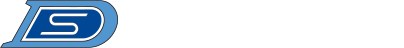電子機器の製造を受託するEMSとは、どのようなサービスなのでしょうか?そこで本記事では、EMSの仕組みやメリット・デメリット、委託先の選び方を分かりやすく解説します。
EMS(電子機器受託製造サービス)とは?
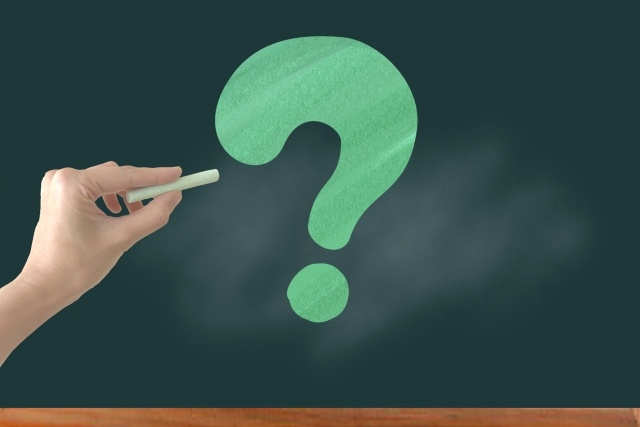
EMS(Electronic Manufacturing Service)とは、電子機器メーカーに代わって製造を受託するサービスです。受託側が部品の調達から組立、検査、出荷までを一貫して代行してくれるため、委託側は開発や販売に専念できます。ここでは、EMSの仕組みや普及した背景、OEM・ODMとの違いを詳しく解説します。
EMSの仕組み
EMSは、電子機器メーカーが設計した製品を、外部の専門工場が製造する仕組みです。メーカーから委託を受けたEMS企業は、電子部品の調達から基板実装、組立、検査、出荷までの一連の工程を担当します。
製造工程には高度な設備や熟練した人材が必要となるため、自社で全てを抱えるとコストや時間がかかります。そのため、製造ノウハウのあるEMS企業に委託することで、品質を保ちながら効率よく製造できるのです。
例えば、スマートフォンや医療機器、車載機器などの製造では、EMSが欠かせない存在になっています。EMSは企業の製造部門を支える外部パートナーとして、重要な役割を果たしているのです。
EMSが普及した背景
EMSが普及した背景には、製造の効率化とグローバル競争への対応があります。EMSのビジネスモデルは1980年代より世界的に普及し、2000年代以降に日本にも広がりました。
電子機器のライフサイクルが短くなり、企業がより早く市場に製品を投入する必要が出てきました。そのため生産設備の投資や人件費が増加し、全工程を自社でまかなうのは難しくなったのです。
そこで、製造工程を外部に委託し、自社は開発やマーケティングに注力するビジネススタイルが一般化しました。特にアジア圏のEMS企業が高品質・低コストの製造体制を整えたことで、世界的な生産ネットワークが確立されています。
EMSの普及は、「スピード・コスト・品質」の最適化を実現する企業戦略の一環として普及してきたのです。
OEM・ODMとの違い
EMSとODM・OEMでは、導入されている分野や設計者、業務範囲などに違いがあります。
| サービスの種類 | 分野 | 設計者 | 業務範囲 |
| EMS (Electronic Manufacturing Service 電子機器の受託製造サービス) | 電子機器 (医療機器・通信機器・車載機器・産業用機器など) | 委託側 | 部品の調達から製品の製造、検査、出荷まで |
| OEM (Original Equipment Manufacturing オリジナル製品の製造受託) | 幅広い製品 (家電・食品・アパレル・化粧品など) | 委託側 | 部品の調達から製品の組立、検査、出荷まで |
| ODM (Original Design Manufacturing オリジナル製品の設計・製造受託) | 幅広い製品 (家電・食品・アパレル・化粧品など) | 受託側 | 製品の設計から部品の調達、製造、検査、出荷まで |
幅広い製品の製造に導入されているOEM・ODMに対して、EMSは電子機器の製造に特化しています。ODMでは受託側が製品の設計も担いますが、EMS・OEMでは委託側が製品の設計を主導するのです。
OEM製造の基礎知識については、次の記事にまとめてありますので、併せてご覧ください。
EMSを活用するメリット

EMS(電子機器受託製造サービス)を活用することで、委託側は製造コストの削減や経営効率の向上を図ることができます。設備投資や人件費の負担を減らし、限られた経営資源をコア業務に集中させられる点が大きな魅力です。ここでは、EMSを活用するメリットについて詳しく解説します。
製造コストを削減できる
EMSを活用する大きなメリットは、製造コストの削減です。EMS企業は大量製造に対応できる体制を整えており、電子部品の一括調達や製造ラインの効率化によってコストを抑えています。
EMS企業は複数の電子機器メーカーから製造を受託しているため、スケールメリットを活かして材料費や人件費を最適化しています。委託側は自社で設備や人員を抱える必要がないため、製造コストを大幅に削減できるのです。
例えば、家電メーカーがプリント基板や電子部品の製造をEMSに委託することで、固定費を変動費に変えて景気変動への柔軟な対応が可能になります。EMSの活用は、製造コストを抑えながら高品質な製品を安定供給できる合理的な選択肢です。
設備投資のリスクを軽減できる
EMSを活用することで、電子機器メーカは高額な設備投資のリスクを避けられます。電子機器の製造には高度な装置やクリーンルーム環境などが必要ですが、自社で全ての設備を整備するには多大な資金が必要です。
EMS企業は最新の製造設備を常に更新し、幅広い電子機器の製造に対応しています。そのため、委託側は初期投資を抑えながら、最先端の製造技術を活用することができるのです。
新しいスマートデバイスの試作や量産を自社で行う場合は、設備投資に莫大な資金が必要になりますが、EMSを活用すれば負担を軽減できます。EMSの活用は、設備投資のリスクを抑えつつ、柔軟な製造体制を確保する有効な手段です。
経営資源を最適化できる
電子機器メーカーがEMSを活用することで、人材・資金・時間といった経営資源をコア業務に集中できます。製造を外部のEMS企業に委託することで、開発やマーケティングなどの付加価値の高い分野にリソースを再配分できるのです。
電子機器の製造には、多くの管理業務(製造計画・部品調達・品質管理など)が発生します。EMS企業に委託すれば、製造管理を効率化し、自社の業務負担を軽減できます。特に、限られた人員で複数の業務を兼務しているベンチャー企業や中小メーカーがEMSを活用することで、開発スピードを上げて製品の市場投入までの時間を短縮することが可能です。
EMSは、経営資源の最適化を進め、競争力を高めるためにも役立ちます。
EMSを活用するデメリット

EMS(電子機器受託製造サービス)には多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットもあります。外部委託することで品質管理が難しく、製造ノウハウが社内に蓄積されにくく、トラブル対応に時間がかかってしまうのです。ここでは、それぞれのデメリットについて詳しく解説します。
品質管理が難しくなる
EMSでは電子機器の製造工程を外部企業に任せるため、自社での品質管理が難しくなります。製品の微細な仕様変更や検査基準などが伝わりにくい場合は、品質にばらつきが生じるリスクがあるのです。
EMS企業は複数のクライアント製品を同時に扱っているため、各社の品質基準を完全に統一することが容易ではありません。また、委託側が現場に常駐できない場合は、検査体制の確認や改善指示に時間がかかることもあります。
特に、通信機器や医療機器などの高い品質が求められる分野では、わずかな不具合でも大きな損失につながることがあります。EMSを活用する際は、信頼性の高い品質管理体制を整備しているEMS企業を選び、定期的な監査や報告体制を整えることが重要です。
製造ノウハウを蓄積できない
EMS企業に電子機器の製造を委託し続けると、委託側の企業内に製造ノウハウが蓄積されにくくなります。製品づくりの工程を外部企業に任せることで、現場で得られる知見や改善方法などのノウハウが自社に残らないためです。
EMS企業が製造工程の改善を担当し、技術情報が委託側に蓄積されない場合は、開発部門が次の製品開発に活かしづらくなります。また、委託側の技術者が製造現場に関わる機会が減ることで、製品全体の理解が浅くなるリスクもあります。
例えば、自社ブランドのスマートデバイスを長期的に展開するなら、製造工程の知見を蓄積しておくことで競争力を維持しやすくなります。EMSを活用する際は、情報共有の仕組みを整え、自社の技術資産を失わない工夫が必要です。
トラブル対応に時間がかかる
EMSを活用する際は、トラブル発生時の対応に時間がかかる傾向があります。自社で製造していないため、原因の特定や修正の指示などのプロセスが複雑になるためです。
特に、製造拠点が海外にある場合や複数の工程を別工場で行っている場合は、情報伝達の遅れや責任範囲の不明確さが発生しやすくなります。また、部品調達の遅延や仕様変更への対応も、委託側と受託側の調整に時間を要するのです。
例えば、EMS企業で製造不良や納期遅延が発生した際に、原因を特定し再発防止策を講じるまでに数週間かかる場合があります。EMSを活用する際は、緊急時の連絡体制や対応ルールを事前に取り決めておくことが重要です。
EMSに関するよくある質問

電子機器メーカーがEMS(電子機器受託製造サービス)の活用を検討する際は、委託先の選び方や対応範囲について疑問を抱くものです。ここでは、「委託先の選び方」「電子機器製造への対応」「国内と海外EMSの違い」といった代表的な質問に分かりやすく回答します。
EMSの委託先をどのように選べばいいですか?
EMSの委託先を選ぶ際は、製造の品質・実績・対応範囲・コストバランスを基準に選ぶことが重要です。単に費用の安さだけで判断すると、品質管理や納期対応などのトラブルが発生するリスクがあります。
EMS企業によって、得意分野や生産規模、設備水準などが大きく異なります。例えば、医療機器や自動車部品など安全性が求められる分野では、「ISO 9001(品質)」「ISO 13485(医療機器・体外診断用医薬品)」などの品質認証を取得している企業を選ぶことが信頼性確保につながります(※)。
電子機器の試作から量産までに一貫して対応できるEMS企業を選ぶことで、設計変更や改良にも柔軟に対応できます。「自社製品の特性とEMS企業の強みが一致しているか」を軸に比較検討することが必要です。
※参照元:
日本品質保証機構「ISO 9001(品質)」(https://www.jqa.jp/service_list/management/service/iso9001/)
日本品質保証機構「ISO 13485(医療機器・体外診断用医薬品)」(https://www.jqa.jp/service_list/management/service/iso13485/)
EMSでどのような電子機器を製造できますか?
EMS(電子機器受託製造)では、幅広い電子機器を製造できます。
- 通信機器(スマートフォン・タブレット・Wi-Fiルータなど)
- 車載機器(カーオーディオ・ドラレコ・ETC車載器など)
- 医療機器(超音波診断装置・心電計・X線検査装置など)
- 産業用機器(検査装置・計測装置・協働ロボットなど)
EMS企業は電子部品の実装や基板製造、組立、検査といった一連の工程を一括管理できる体制を整えて、高い精度と安定した品質を実現しています。また、クリーンルームや自動検査装置などの設備を備えており、精密機器の製造にも対応可能です。
スマートデバイスやIoT機器のように小型で複雑な電子機器でも、EMSの高度な製造技術によって効率的に量産できます。EMSは、家庭用から産業用まで幅広い電子機器の製造を支えている重要なパートナーです。
国内と海外のEMSに違いはありますか?
一般的に、国内EMS企業は品質と迅速な対応力に優れ、海外EMS企業はコスト面で有利です。
| 違い/EMSの拠点 | 国内 | 海外(主にアジア圏) |
| コスト | 人件費や設備費が高い | 人件費が安く、大量製造に向いている |
| 納期 | 距離が近いため、変更や短納期に対応できる | 距離と時差があるため、変更や調整に時間がかかる |
| 対応力 | 言語や文化が共通しているため、スムーズ | 言語・文化の違いから、意思疎通に手間がかかる |
国内と海外のどちらのEMSを選ぶかは、電子機器の特徴や製造量、納期などの観点から総合的に判断してください。開発段階では国内EMS企業で試作を行い、量産段階で海外EMS企業に移行する「ハイブリッド委託」を採用することも可能です。
EMSの委託先を検討しよう!
EMS(電子機器受託製造サービス)は、製造のコスト削減や効率化を実現できる有効な手段です。自社の電子機器の特徴や製造体制に合う委託先を選び、長期的な事業成長につなげましょう。
三信電気株式会社では、電子機器の企画・設計から試作、部品調達、信頼性評価、実装、組立、量産までに一貫して対応しています。
半導体商社としての実績と国内外のネットワークを活かし、低コスト・短納期・高品質な電子機器の開発・製造をサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。