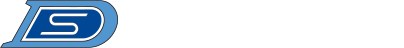「現場のムダを減らしたい」「人手不足で手が回らない」「AI導入って結局コストが高いだけ?」そんな悩みを抱える企業が、今“エッジAI”に注目しています。
クラウドに頼らず、その場で即判断・即処理できるから、生産現場・建設・インフラなど“時間と安全が命”の現場にぴったり。
本記事では、エッジAIの基礎から導入企業のリアルな事例、成果につながる導入パートナーの選び方までを徹底解説。最小コストで最大効果を出すヒントが詰まっています。
エッジAIとは?クラウドAIとの違いと企業が注目する理由
エッジAIとは、クラウドにデータを送信せず、現場の端末でリアルタイムに処理を行うAI技術です。通信の遅延やセキュリティリスクを回避できることから、スピードと安全性が求められる現場で導入が進んでいます。ここでは、クラウドAIとの違いと、エッジAIの具体的なメリットを解説します。
クラウドAIとの比較でわかる「リアルタイム処理」の強み
エッジAIとクラウドAIの比較表
| 比較項目 | エッジAI | クラウドAI |
| 処理場所 | デバイス近傍(エッジデバイス、オンプレミスサーバー) | データセンター(クラウドサーバー) |
| リアルタイム性 | 非常に高い(遅延が少ない) | 比較的低い(通信遅延が発生しうる) |
| 通信環境への依存度 | 低い(オフラインでも限定的な処理が可能) | 高い(常時安定したインターネット接続が必要) |
| データセキュリティ | 比較的高い(機密データをローカルで処理可能) | データ送信時・保管時の対策が別途必要 |
| 通信コスト | 低い(必要なデータのみ送信、または送信不要) | 高い(大量のデータをクラウドに送信する場合) |
| 導入・運用コスト | エッジデバイスの導入コスト、運用保守体制 | クラウドサービス利用料、データ転送量に応じた費用 |
クラウドAIとエッジAIは、処理場所・速度・コストなどの点で大きく異なります。特に「リアルタイム性」はエッジAIの最大の強みです。クラウドAIでは、データをサーバーへ送信して処理するためタイムラグが発生しますが、エッジAIは現場で直接処理するため、即時の応答が可能です。
たとえば、異常検知や緊急制御が必要な製造現場やインフラ点検、作業員の安全管理など、判断に遅れが許されないシーンで、ミリ秒単位の処理を実現できます。
さらに、以下のような点でエッジAIは優れています。
- 通信環境への依存度が低い:山間部やトンネルなどでも機能
- セキュリティ性が高い:機密データをローカル処理
- 通信コスト削減:必要最小限の情報のみ送信
こうした特徴から、エッジAIは、製造・建設・社会インフラといった「現場」において、今後ますます欠かせない存在となっていくでしょう。
製造・建設・インフラ現場がエッジAIを求める3つの理由
製造業や建設業、インフラ管理など、リアルタイム性が重視される「現場」では、エッジAIの導入が加速しています。その背景には、共通の課題とエッジAIならではの解決力があります。
理由①:即時性が求められる判断・制御への対応
- 製品異常の即時検知や品質チェック
- 建設現場での重機接近警告、侵入検知
- インフラの突発的トラブルへの即応
エッジAIなら、センサーや映像のデータをその場で分析し、 リアルタイム制御やアラート発報が可能。 「すぐに判断・すぐに動く」が実現します。
理由②:通信インフラの制約とコスト対策
- 工場の広域エリア
- 山間部・地下トンネルなどの通信不安定エリア
- 点在するインフラ設備(ダム・電柱・交通制御など)
エッジAIは、 必要な情報だけをクラウドに送信する「前処理フィルター」に。通信量とコストを大幅に削減できます。
理由③:データセキュリティとプライバシー保護
- 製造ノウハウなどの機密情報
- 顔・行動が記録された映像データ
ローカルで完結する処理が可能なエッジAIなら、外部送信を最小限に抑え、ガバナンスやコンプライアンス対策にも効果的です。
現場で即断即決・低コスト・高セキュリティを実現する手段として、エッジAIは今後ますます不可欠なテクノロジーと言えるでしょう。
エッジAIは必要か?導入を検討すべき企業の課題とは

多くの企業が抱える課題の中には、エッジAIの導入によって解決の糸口が見えるものがあります。もし、あなたのビジネスや現場が以下のような状況に直面しているのであれば、エッジAIの活用を具体的に検討するタイミングかもしれません。
「不良率が下がらない」「人手不足」「リアルタイム判断ができない」
製造・建設・インフラ現場では、「不良率が下がらない」「人手が足りない」「即時対応ができない」といった課題が共通して見られます。これらは従来の手法では限界があり、解決の糸口が見えにくい問題でもあります。そんな中で注目されているのが“エッジAI”の活用です。具体的にどのような現場課題を、どのように解決できるのかを、以下に整理しました。
導入企業に共通する“3つの悩み”
エッジAIの導入を検討、あるいは既に導入して成果を上げている企業には、その背景に共通する悩みや課題意識が見られます。具体的には、以下の3つのポイントが挙げられます。これらの悩みは、エッジAI導入の検討を後押しする重要な動機となっています。
悩み①:DX推進の遅れと現場データの未活用
DXの必要性は理解していても、現場のデータ活用は思うように進まず、通信コストやセキュリティへの懸念、リアルタイム性の課題が壁になります。エッジAIは、現場で即時にデータを処理・分析できるため、情報の鮮度を保ったまま素早い意思決定に活かせます。
悩み②:既存設備への追加投資とシステム連携の複雑さ
新技術を導入しようとしても、既存設備との連携や大規模なシステム改修がネックになります。エッジAIは、既存のカメラやセンサー、PLCに後付けで導入できるソリューションも多く、小規模投資から段階的に導入効果を確かめられます。
悩み③:PoC止まりで終わる導入プロセス
PoCで手応えを感じても、そこから先の本格導入に進めない企業が少なくありません。エッジAIはスモールスタートが可能で、現場単位での導入から全社展開まで移行しやすいのが特徴。既存システムへの負担も小さく、展開がスムーズです。
成果が出た!エッジAI導入企業の成功事例【3選】

エッジAIは、既に多くの企業や組織で導入が進み、具体的な成果を生み出しています。ここでは、製造業、建設業、そして地方自治体における、特に注目すべき3つの導入事例を詳しくご紹介します。これらの事例から、エッジAIがどのように“現場のムダ”を削減し、リアルタイム処理によって課題を解決するのか、その具体的な活用方法と効果をご覧ください。
事例①:物流現場の生産性を刷新 ― AMR×エッジAIで作業効率を大幅改善【N社】
背景と課題
中堅物流企業のN社では、熟練スタッフの退職や人手不足が深刻化し、ピッキング精度や処理スピードの低下が業務効率を圧迫していました。また、誤ピッキングによる返品やクレーム対応の増加も、現場の課題として顕在化していました。
エッジAI導入の概要
| 項目 | 内容 |
| 導入前の課題 | ピッキングミスの多発、作業効率の低下、人材育成の負担増大 |
| 導入ソリューション | AMRとエッジAIカメラを連携させたピッキング支援システムを導入 |
| 処理方式 | エッジデバイス上で画像解析を即時実施。クラウド接続不要でリアルタイムフィードバック |
| 主な導入効果 | 作業効率1.8倍、ピッキングミス72%削減、1時間あたり処理件数2.3倍向上 |
導入の成果とポイント
N社では、作業棚の位置情報に基づきAMRがピッキング地点まで作業者を誘導し、商品選定時にはエッジAIがリアルタイムで画像解析を行い、ミスがあれば即座にアラートを表示する仕組みを構築しました。
これにより、新人でもベテラン並みの精度で作業ができるようになり、1時間あたりの処理件数は2.3倍に向上。ピッキングミスは72%削減され、再配送や返品対応にかかるコストも大幅に削減されました。
さらに、AMRとエッジAIの連携によって人と機械の動線が最適化され、全体の作業効率は1.8倍に改善。教育コストの削減にもつながり、業務の属人化を解消する大きな一歩となりました。
N社の取り組みは、物流業界における省人化・高効率化を実現するDXの先進事例として注目を集めています。
事例②:エッジAIカメラで工場の品質管理を革新【B社】
背景と課題
大手製造業のB社では、製品の高品質化が進む中で、従来の目視検査やルールベースの画像処理では検査精度とスピードに限界が生じていました。とくに微細な不良の見逃しや、検査員のスキル差によるばらつきが課題となっていました。
エッジAI導入の概要
| 項目 | 内容 |
| 導入前の課題 | 目視検査によるヒューマンエラー、検査員の熟練度依存、検査スピードの限界、不良品流出リスクによるブランドイメージ低下の懸念 |
| 導入ソリューション | AIチップを内蔵したエッジAIカメラを製造ラインに設置し、傷・汚れ・異物混入・形状不良などをリアルタイムで自動検出 |
| 処理方式 | 学習済みAIモデルによるエッジ側での高速処理により、クラウド依存なしで即時判定が可能 |
| 主な導入効果 | 不良品検出率の大幅改善、検査スピードと生産性の向上、検査員の負担軽減、品質改善に向けたデータ活用 |
導入の成果とポイント
B社ではエッジAI検査カメラの導入により、従来では見逃されていた微細な欠陥も安定して検出できるようになり、製品品質の信頼性が大きく向上しました。
エッジ側で即時に処理されることで、不良品が次工程へ進む前にリアルタイムでフィードバックされ、流出リスクを大幅に軽減できています。
さらに、検査データを蓄積・分析することで、歩留まり改善やプロセス最適化が進み、結果的に工場全体の競争力強化にもつながっています。人的リソースをより重要な工程に集中させることが可能になり、省人化・効率化の両立が実現しました。
事例③:ため池の巡回作業を自動化し、防災力を強化【鳥取県】
背景と課題
鳥取県では、県内に多数存在するため池の管理において、豪雨時の水位監視や堤防異常の早期発見が重要な防災・減災対策となっていました。
しかし、広範囲に点在するため池を人手で巡回・点検するのは大きな負担であり、特に豪雨や台風時には職員の安全も懸念されていました。
エッジAI導入の概要
| 項目 | 内容 |
| 導入前の課題 | 広範囲なため池の定期巡回にかかる人的・時間的コスト。豪雨時など危険な状況下での点検作業のリスク。異常発見の遅れによる被害拡大の懸念 |
| 導入ソリューション | エッジAI搭載のセンサー・監視カメラを各ため池に設置。水位・水質・堤防の変状をAIがリアルタイムで監視し、異常時に自動通知 |
| 処理方式 | センサーから得たデータを現地で即時処理。通信環境が不安定な地域でも稼働し、クラウドへの常時接続不要 |
| 主な導入効果 | 巡回点検作業の大幅な効率化と省人化、危険作業の回避による職員の安全確保、異常の早期発見による災害被害の軽減、予防保全の高度化 |
導入の成果とポイント
このエッジAIを活用した監視システムの導入により、鳥取県では職員が遠隔地からでもリアルタイムにため池の状態を把握できるようになりました。
とくに台風や集中豪雨時において、現場へ赴くことなく水位上昇や異常を察知できるため、迅速かつ的確な避難判断と情報伝達が可能になり、地域住民の命を守る重要な手段となっています。
また、この取り組みは国土強靭化やスマートシティ推進の文脈でも注目されており、他の自治体からの視察や問い合わせも増えています。
導入で失敗しない!エッジAIパートナーの選び方と三信電気が選ばれる理由
エッジAIプロジェクトの成功は、適切な導入パートナー選びに大きく左右されます。単に技術を提供するだけでなく、お客様のビジネス課題を深く理解し、共に解決策を模索してくれるパートナーを見極めることが重要です。ここでは、多くの成功企業がパートナー選定において重視したポイントを解説します。
「PoC対応できるか?」「ハードとセットで提案できるか?」
エッジAI導入のパートナーとして、三信電気が選ばれる理由は以下の3点です。
- 多様な業界での豊富な実績
製造業の業務効率改善、建設現場での安全管理、インフラ監視など、幅広い分野での導入実績があります。業界特有の課題に対応できる知見が強みです。 - PoCから運用までの一貫サポート
課題のヒアリングからPoC、本格導入、運用保守までワンストップで支援。プロジェクトの全フェーズを安心して任せられます。 - 最適なハードウェア選定と安定供給
独立系商社としての経験を活かし、幅広いメーカー製品から最適な機器を中立的に選定。安定的な調達力も評価されています。
エッジAI導入のパートナー選びでお悩みの際は、これらのポイントを参考に、ぜひ一度三信電気にご相談ください。お客様のビジネス革新を力強くサポートいたします。
【無料相談OK】エッジAI導入前にできることとPoCまでの流れ
「エッジAIを導入したいが、何から始めればいいか分からない…」
そんな企業様に向けて、三信電気では無料相談〜PoC(概念実証)までをワンストップでサポートしています。
▼ 無料相談でできること
- 現場課題のヒアリング
- ユースケースや導入効果のご提案
- PoC実施に向けたスケジュール・予算相談
▼ PoC〜導入までの流れ
- 初回相談・課題整理
- PoC(小規模検証)実施
- 本格導入プランのご提案
- 構築・運用保守まで一貫対応
まとめ:エッジAIの導入は“スモールスタート”から!現場に合わせて最適化を
エッジAIは、現場で発生する問題をリアルタイムで処理し、不良品削減・省人化・安全性向上など、多くの課題に直接アプローチできる最新技術です。
しかし、成果を出すには製品導入だけでは不十分。
PoC(実証実験)から本導入、運用まで一貫してサポートできるパートナー、そして中立的な立場で最適なハードウェアを選定できる提案力が成功の鍵となります。
三信電気では、これまでに製造・建設・社会インフラなど多様な業界での導入実績を積み重ね、PoCから現場適用までをトータルで支援しています。
無料相談でできること(一部)
- 課題のヒアリングと活用可能性のアドバイス
- エッジAIに適した活用シーンのご提案
- PoCの進め方や費用感についてのご説明
- 実績事例のご紹介と比較検討のポイント整理
→ まずは無料相談をご利用ください。
現場課題の「見える化」から「解決」への第一歩を、今ここから始めましょう。